
人生100年時代と言われる現代において、将来の判断能力低下に備えることは、終活における重要な要素の一つです。
認知症や病気により判断能力が低下した際に、自分らしい生活を維持し、財産を適切に管理するために「成年後見制度」があります。
この制度を正しく理解し、適切に活用することで、安心した老後生活を送ることができます。
成年後見制度とは何か
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった成年者を保護し、支援する制度です。
本人の権利を守り、財産管理や身上監護を行うことで、その人らしい生活を継続できるよう支援することを目的としています。
この制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、それぞれ異なる特徴と活用方法があります。
自分の状況や希望に応じて、どちらを選択するかを検討することが重要です。
法定後見制度の種類と申立方法
法定後見制度の3つの類型
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています。
後見(こうけん)
判断能力が欠けているのが通常の状態にある人が対象です。
日常生活に関する行為以外のすべての法律行為について、成年後見人が代理権を持ちます。また、本人が行った法律行為を後から取り消すことも可能です。
保佐(ほさ)
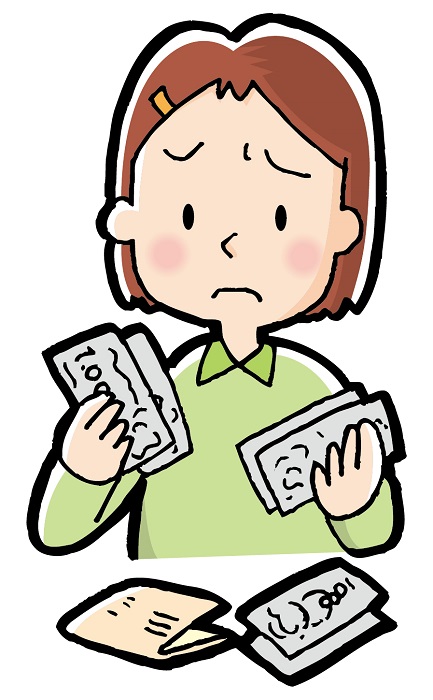
判断能力が著しく不十分な人が対象です。
借金、訴訟、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの重要な法律行為について、保佐人の同意が必要になります。
同意を得ずに行った行為は取り消すことができます。
補助(ほじょ)
判断能力が不十分な人が対象です。
特定の法律行為について、家庭裁判所が補助人に同意権や代理権を与えます。
最も軽度な支援形態で、本人の自己決定権を最大限尊重します。
申立の手続き
法定後見制度の申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官などです。
申立には以下の書類が必要です
- 申立書
- 本人の戸籍謄本、住民票
- 後見人等候補者の戸籍謄本、住民票
- 本人の診断書
- 本人の財産に関する資料
- 後見等に関する申立事情説明書
申立費用として、収入印紙800円、登記印紙2,600円、郵便切手代などが必要です。
また、医師による鑑定が必要な場合は、別途鑑定費用(5万円~15万円程度)がかかることがあります。
任意後見制度の活用法
任意後見制度の特徴
任意後見制度は、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に代理権を与える契約を結ぶ制度です。

この制度の最大の特徴は、本人の意思を反映できることです。
誰に後見人になってもらいたいか、どのような支援を受けたいかを、元気なうちに自分で決めることができます。
任意後見契約の締結方法
任意後見契約は、公正証書によって締結する必要があります。
公証人が本人の意思能力を確認し、契約内容を明確に記録します。
契約には以下の内容を定めます:
- 任意後見人となる人
- 任意後見人に委任する事務の内容
- 報酬に関する事項
- その他必要な事項
契約締結後、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、任意後見が開始されます。
移行型と即効型
任意後見制度には、移行型と即効型があります。
移行型は、まず見守り契約や財産管理委任契約を結び、判断能力が低下した時点で任意後見契約に移行する方法です。
継続的な支援関係を築けるため、より安心できる制度です。
即効型は、契約締結後すぐに任意後見監督人の選任を申し立てる方法です。
軽度の認知症などで、早期の支援が必要な場合に利用されます。
後見人の選び方と注意点
後見人の種類
後見人には、親族が選ばれる場合と、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選ばれる場合があります。
近年は、複雑な財産管理や家族間の対立がある場合を中心に、専門職後見人が選任されることが増えています。
良い後見人の条件
良い後見人を選ぶ際のポイントは以下の通りです:
- 本人との信頼関係があること
- 誠実で責任感が強いこと
- 必要な時間を確保できること
- 基本的な法律知識や財産管理能力があること
- 本人の意思を尊重する姿勢があること
注意すべき点
後見人選任においては、以下の点に注意が必要です:
家庭裁判所が最終決定する
法定後見制度では、申立時に候補者を挙げることはできますが、最終的には家庭裁判所が適任者を選任します。
必ずしも希望通りの人が選ばれるとは限りません。
長期間の関係になる
後見人の役割は、本人が亡くなるまで続く可能性があります。
長期的な視点で、継続して職務を遂行できる人を選ぶことが重要です。
利益相反の問題
後見人と本人の間で利益が対立する場合があります。
このような場合には、家庭裁判所が特別代理人を選任することになります。
後見制度支援信託の仕組み
後見制度支援信託とは
後見制度支援信託は、成年後見制度を利用している人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。
制度の目的と効果
この制度の主な目的は、被後見人等の財産の安全性を高めることです。
大きな財産を信託することで、後見人による不正使用を防止し、必要な時に確実に財産を活用できるようになります。
信託財産を払い戻すには家庭裁判所の指示書が必要なため、高額な支出については裁判所のチェックが入る仕組みになっています。
利用の流れ
後見制度支援信託の利用は以下の流れで行われます
- 家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を検討
- 専門職後見人が一時的に選任される場合がある
- 信託契約の内容について家庭裁判所と協議
- 信託銀行等と信託契約を締結
- 信託開始後の後見人の変更(必要に応じて)
まとめ:早めの準備で安心の将来を
成年後見制度は、判断能力の低下に備える重要な制度です。
法定後見制度と任意後見制度それぞれの特徴を理解し、自分の状況や希望に応じて適切な制度を選択することが大切です。
特に任意後見制度は、自分の意思を反映できる制度であるため、元気なうちに検討することをお勧めします。
また、後見制度支援信託などの財産保護の仕組みも併せて理解しておくことで、より安心して制度を利用することができるでしょう。
終活の一環として、これらの制度について家族と話し合い、必要に応じて専門家に相談することで、将来への不安を軽減し、自分らしい人生を最後まで送ることができるのです。

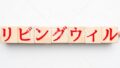

コメント